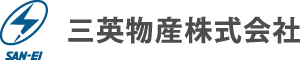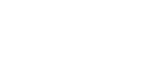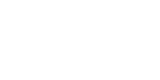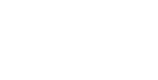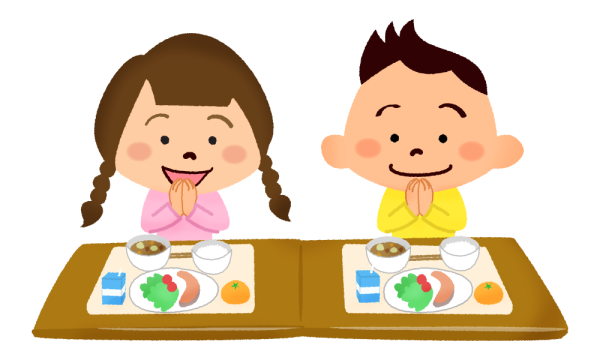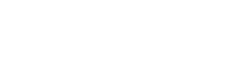| 2025年10月1日 |
| 給食について(第9回) |
前回の第8回でご紹介した「学校給食衛生管理基準」のおさらいをしたいと思います。 〇局長通知「学校給食衛生管理の基準」
学校給食法改正の主な目的は、「安全・安心な給食の実施」と「食育の推進」にあります。
少し難しい話しになってしまいましたが、給食施設を計画する際は避けて通れない部分です。 皆さんの近くの給食施設も、このような法令の基に成り立っているので、機会があれば少し調べてみると面白いかもしれません。 |
| 2025年5月28日 |
| 給食について(第8回) |
みなさんは給食にも法律が存在するのをご存知でしょうか。 この基準はマニュアル化されており、様々な決まりごとが書かれています。 今回はこのマニュアルの中からいくつか抜粋してご紹介したいと思います。 【A】(1)学校給食施設 【B】(2)学校給食設備 【C】(3)食品の検収・保管等 ※文部科学省「学校給食衛生管理基準」より抜粋 |
| 2025年1月10日 |
| 給食について(第7回) |
みなさんは「全国学校給食甲子園」という大会をご存知でしょうか。 2006年に第1回大会が開催され、2024年は第19回目になります。 茨城県では、2021年の第16回大会で、ひたちなか市の美乃浜学園が優勝を飾っております。 参考までに運営サイトのURLを添付しておきます。 |
| 2024年8月26日 |
| 給食について(第6回) |
第6回のテーマは、「給食の献立」について触れたいと思います。 「学校給食摂取基準」に基づき、各地域の栄養教諭等により作られています。 その中でも不足しがちなカルシウムに関しては、給食で多目に摂取出来るよう配慮されているようです。 濃い味付けに慣れてしまっていると、給食が薄味に感じるかもしれません。 子どもの時とは違う、新たな発見があるかもしれません。
|
| 2024年5月15日 |
| 給食について(第5回) |
第5回のテーマは、「給食で使用する食器」について少し触れたいと思います。 ■昭和~ ■昭和~平成 ■平成~令和 |